資格取得までの総勉強時間が多いものは、
1年単位以上のスパンで勉強をしていくこともあります。
1年に1回の受験の場合は、
直前期のように集中して勉強できているものでしょうか?
パーキンソンの法則とは?
パーキンソンの法則とは、イギリスの歴史学者・政治学者であるシリル・ノースコート・パーキンソンが、著書「パーキンソンの法則:進歩の追求」で提唱した法則です。
(残念ながら、この本は1960年発行のようで、なかなか高価な本となっています。)
以下の2つの法則から成り立っています。
- 第1法則「仕事の量は完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」
- 第2法則「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する」
令和3年度の中小企業診断士第1次試験が予想より1か月後になりました。
その時私は…
夏休みの宿題を最後に慌てる
思い当たる人は多いのではないでしょうか。
毎年のことなので、今年こそは!と思っても
またまた明日から学校だーとなって頑張る。
大人になっても、納期に余裕があるとき、
集中してやれば早めに納めることができても、
納期直前に集中して頑張り納期ギリギリになる。
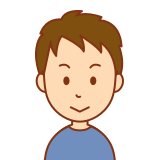
余裕があると、ついつい後回しに
このような自動調整を
知らず知らずのうちにやってしまいがちです。
中小企業診断士 第1次試験 令和3年は後ろ倒し
何の試験でもそうですが、
受験日に合わせてスケジューリングを行っていきます。
中小企業診断士の第1次試験に場合、暗記科目というものがあり
2次試験に関係無い科目、あまり関係のない科目もあり
直前期に暗記するという人もいます。
そのため、試験日がいつかということは非常に大切になります。
令和元年までは毎年8月1週目の土日
昨年令和2年は、東京オリパラ開催予定であったため、
7月2週目の土日となっていました。
今年はいつ?が試験案内が出るまでの分かりませんでした。
多くの人は、東京オリンピック開催前の7月予想でした。
結果は、
東京オリンピックと東京パラリンピックそれぞれの開催期間の間の
8月21日(土)・22日(日)でした。
予想より1か月延びた感じです。
-e1630674327213.jpg)
1か月の余裕ができた~!
期間延長にどう対応するか?
試験案内から1次試験までの期間が
1か月程度延びました。
それまでの予定通りに勉強を進め
残りの1か月を再調整
すればよかったのですが…
ここで、余裕ができてしまったのです💦
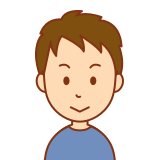
余裕ができたので、ちょっと別のテキストを見てみよう
そうなんです。
本来であれば、苦手科目である経済学・経済政策の
勉強に集中する予定でしたが、
その他科目の別のテキストや参考となりそうな書籍に
眼が行ってしまいました。
完全に1か月後回しです。
以下、言い訳がクドクド入ります。
ところが、8月になると特需的な業務が入り勉強時間が
取れなくなるという事態になってしまいました。
朝早くからの業務のため、朝勉はできず、日中も隙間時間は無し
夜も不慣れな業務と緊張感のある業務ということもあり
半分寝ながらの勉強となってしまいました。
直前期でなければ完全に寝ていました。
当初予定通り勉強すれば特に問題なしでした。
期間の長い勉強に集中する方法
数年前までマラソンを走っていました。
足首を痛めてしまい、それから徐々に離れてしまいましたが、
それまでは、毎週末は集中して走り、月100㎞超は走っていました。
長い距離を走るのに慣れてくると意識しませんでしたが、
当初は走り続けるために意識したことがあります。
それは、
次のあの柱まで走る
次のあの信号まで走る
そうです。
すぐ目前の、でも少し頑張らなければならない程度を目標に
定め頑張りました。
すると、走れるものです。
そこまで走りきると、もっと先までとなります。
これが、その間隔が長くなり、
いつの間にか意識しなくなっていきました。
中小企業診断士の1次試験であれば、
7科目があります。
1科目100時間~150時間と言われますが、
1か月に1科目程度でしょうか。
1周まわしてみて、
不足箇所や苦手箇所の克服に充てるという流れだと思いますが、
そのために「模試」を使うことが多いと思います。
実は、私は模試を1回も受けませんでした。
試験時間を測り科目単位の過去問を解いたのは
直前に1年度分を1回だけでした。
自分の立ち位置も確認せずに進めたことになります。
また、科目単位になりますが、
その分野の別資格を取得するという方法もあります。
例えば、
「経営情報システム」の場合であれば
応用情報技術者の試験を受ける
「財務・会計」であれば
簿記2級の試験を受ける
といった
科目に関連する資格試験を受けてみるのも
良いのではないでしょうか。
応用情報技術者のこちらのテキストは
経営情報システムテキストの内容に近いと思います。
イラスト入りで、経営情報システムのテキストより分かりやすいかもしれません。
試験日は4月で、来年の科目免除目的には使えませんが、
模試以上に効果はあるのではないかと思っています。
財務・会計は科目合格していると思いますが、
もう少し別の視点から勉強してみようと思います。
同じ角度から見るだけでなく別角度から見ることでしっかりと見えることがあると思います。
最初に出てくる株式会社や会社合併等は「経営法務」にも関わり、分かりやすいです。
ただ、これら関連資格取得は、あくまでも主目標である中小企業診断士試験合格のための手段の一つです。あまり時間を取られ過ぎると本末転倒となりますので、ご注意を!
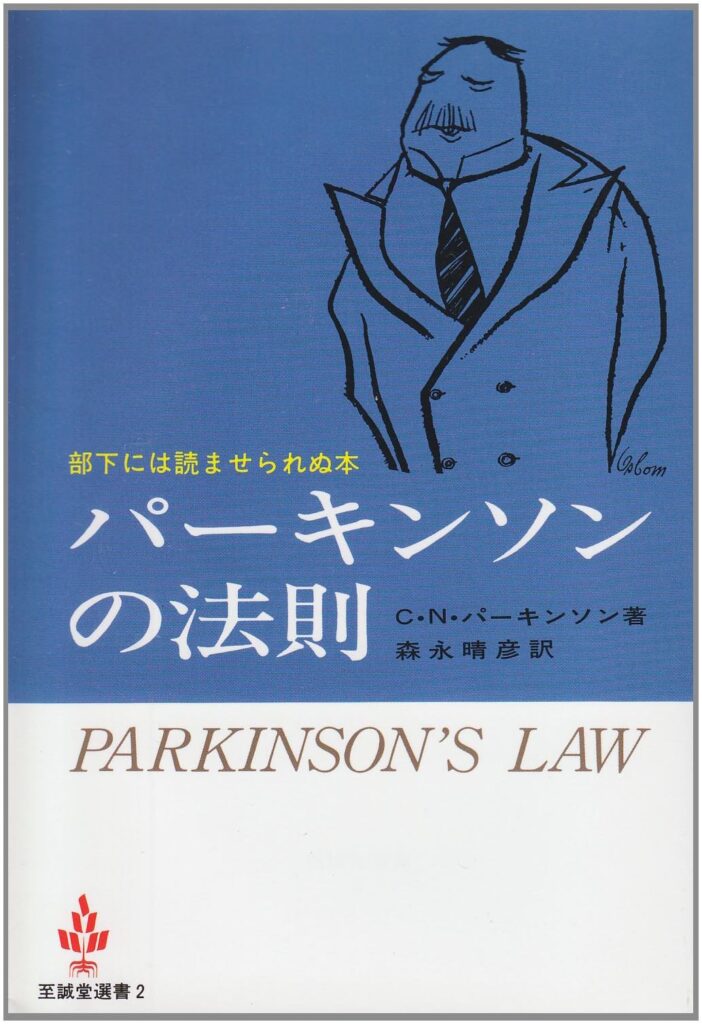


コメント