令和6年8月3日(土)に受験した、
令和6年度中小企業診断士第1次試験の財務・会計
試験終了の翌日5日(月)に公表された正解と配点を元に
実施した自己採点で問題を見て以来
約8カ月ぶりに立ち向かってみました。
過去問をダウンロードしてタブレット端末で実施
中小企業診断協会のホームパージから問題を
タブレッド端末にダウンロードし実施
まず、
第一問目から、
「アレ!?こんな問題やったっけ?」
「別の年度の問題をダウンロードしたのか?」
でした💦
忘却曲線でもゼロにはならないですよね?
パソコンで資料を作っている途中、電源が切れて真っ新になっても
記憶は残っているため同じ時間はかからずできるもの
ところが、
全くの初見状態でした。
もう、笑うしかありません。
8カ月ぶりにやった結果は?
結果は、昨年の本番より
1問正答数が少ない結果でした😢
1問4点の配点ですから、4点ダウンです。
面白いのは、時間を取られた問題に
最後はアキラメテ適当に解答したものに
「テキトー」と記入したのですが、
昨年本番の問題用紙にも同じく「テキトー」と書かれていました。
財務・会計は2次試験でも事例Ⅳが勝負の分かれ目となるような
重要な科目です。
2次試験2度受験の経験からも
最重要科目だと感じています。
(だったら、勉強空白期間を無くせ!と自らツッコむ)
令和7年度の今年も財務・会計を受験し
得点源にしようと考えていました。
(いや、います!!!!!)
計算問題の対応
1次試験は電卓が使えないため、如何に間違わずに時間を短縮できるかが重要になりますね。
令和6年度の問題では、以下の計算問題がありました。
第 7問 CF計算
第10問 原価計算
第12問 CVP分析 設問1、2
第14問 WACC
第21問 サステナブル成長率
第22問 割引現在価値
第24問 通貨オプション
個人的には、2次でも重要となってくる、CF計算、原価計算、CVP分析は落としたくない思いが強いですが、この3つは計算は比較的簡単でした。
暗算でも可能な感じでしたが、念のため間違った時用に筆算しました。
令和5年度2次試験事例Ⅳでは、CVP分析の問題で、絶対落とさないつもりが検算で合わずに、何度もやり直し(結果正答ではありました)、NPVの問題が手つかずになってしまったという苦い思い出があります。
1次の場合、難しい計算も簡単な計算も配点は同じ4点なんですよね。
焦っていいことはなし、取り敢えず後回しでも良いのかなと思います。
今後、どう勉強していくか
昨年の本番でも感じたのですが、
まず過去問題集だけやっていても点数は伸びない!
今年は、TACのスピード問題集を購入し1周やりましたが、
これだけでも対応しきれません。
8カ月ぶりにやっても、ほぼ同じ結果でしたが、
実は正答・誤答箇所はほぼ同じです。
今回勘違いした凡ミスがありましたが。
ということは、今までと同じ勉強方法では
得点が伸びないということは明白になりました。
では、どうするか
単純に計算式を覚えていても
変化球には対処できません。
つまり、知識不足
何故、この計算式となっているのかを説明できるレベルにすること
暗記には当日の振り返りが有効ということも分かってきました。
更に知識の深堀りのためには、他人に説明できること
架空の第三者に説明する振り返りをやっていきたいと思います。
過去問を何周回したかはもう問いません。
今までは、
効率よく苦手科目は足切り回避し、60点アベレージを目指していました。
実際、得意科目以外の全科目ほぼ60点に近い科目合格で合格し、
二次試験もあと数点で残念な結果であり
今までのやり方で良いのだと
勘違いしていたことに気づきました。
ストレート合格する人などを見てみると
主要3科目はかなり高得点で突破しています。
そういうことですよね。
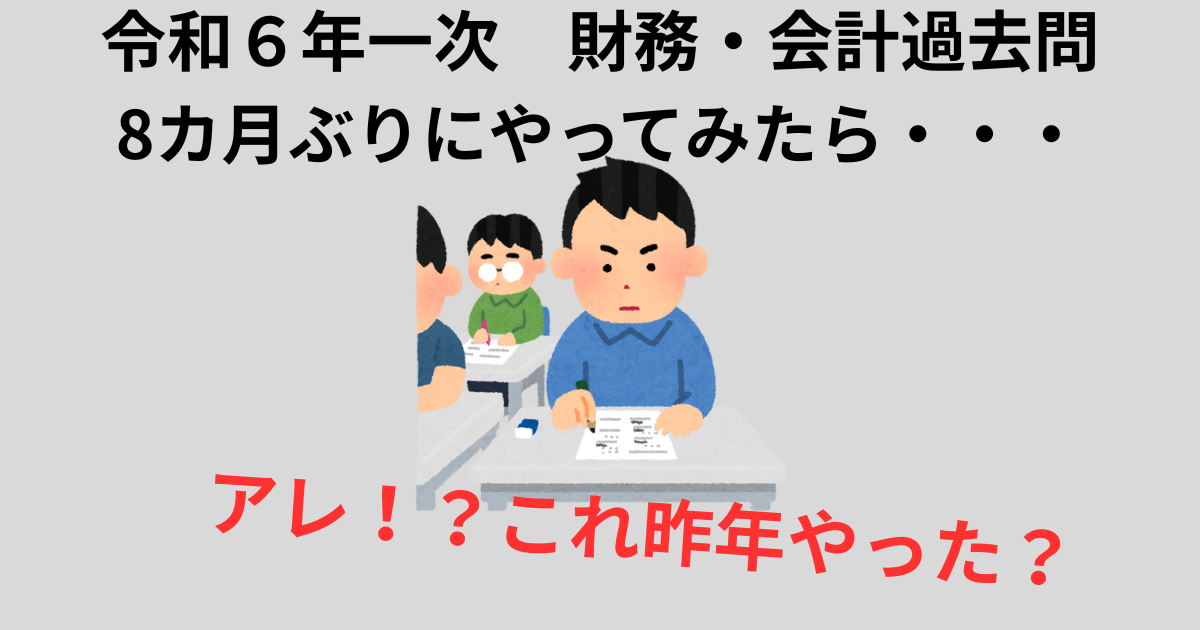
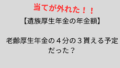
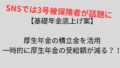
コメント